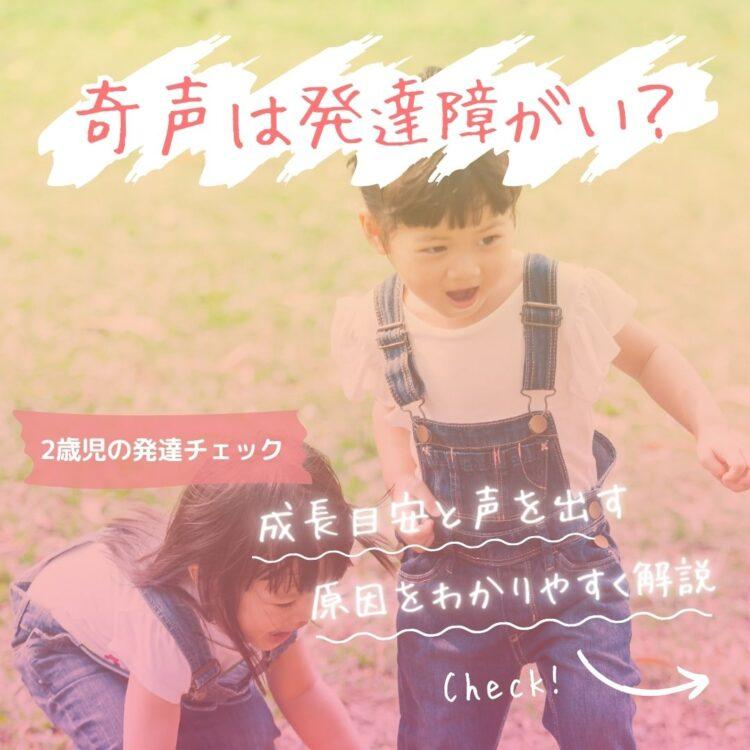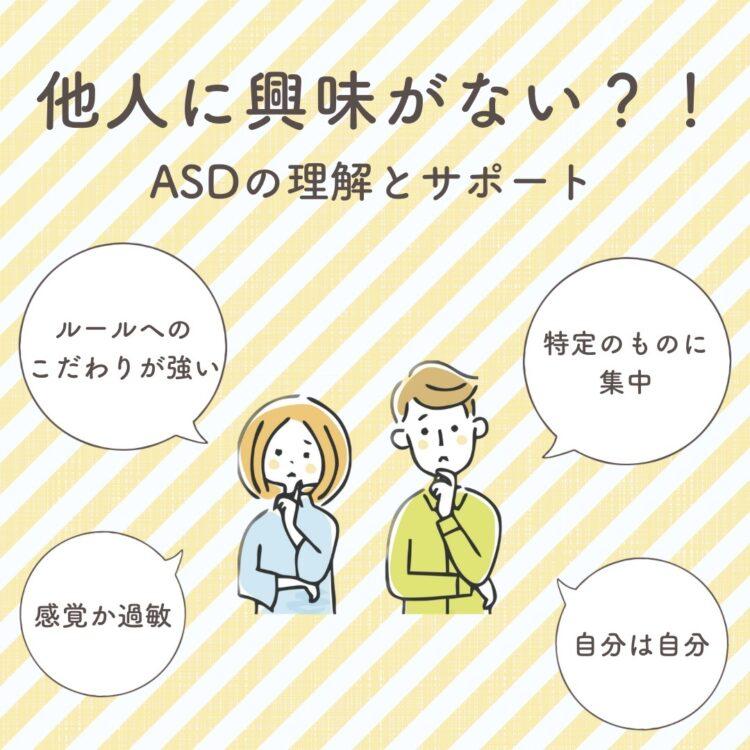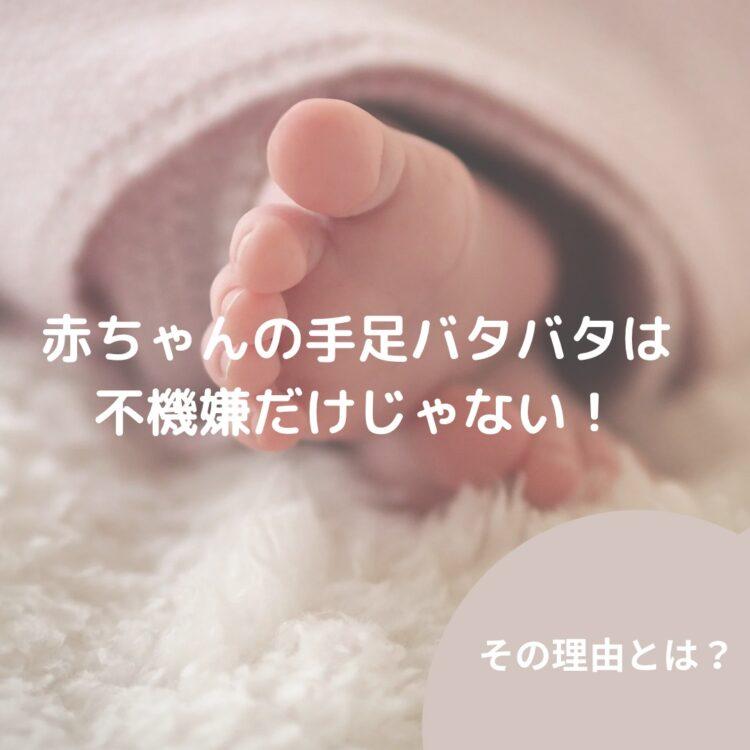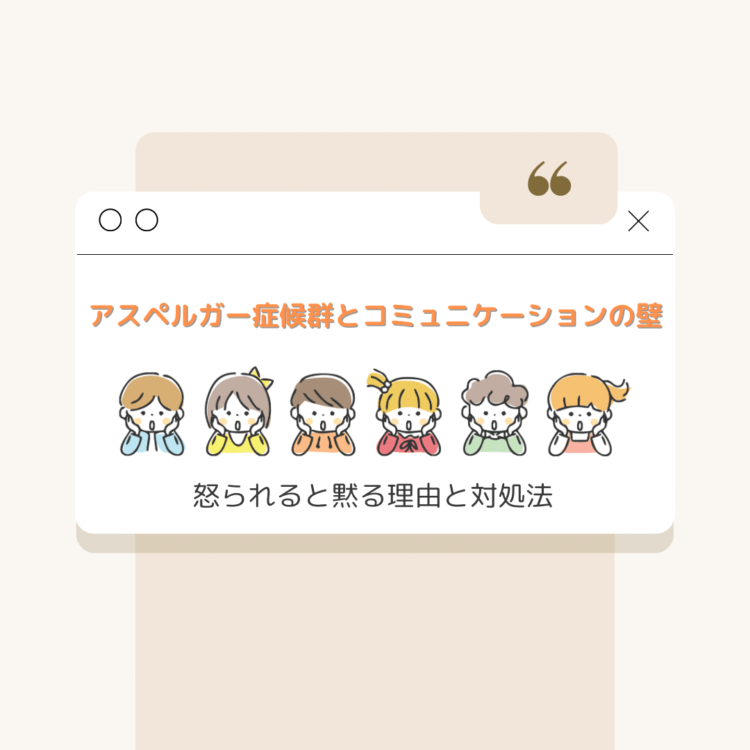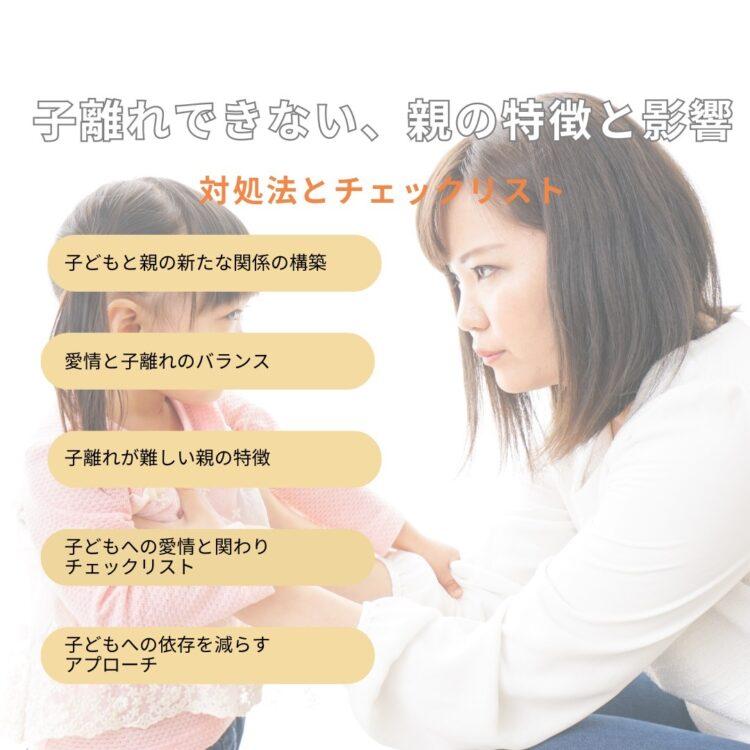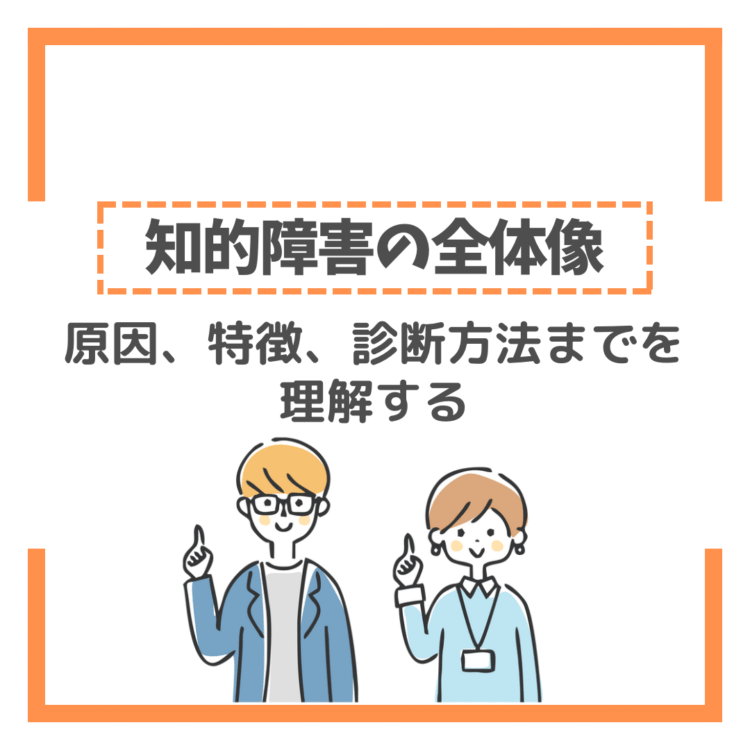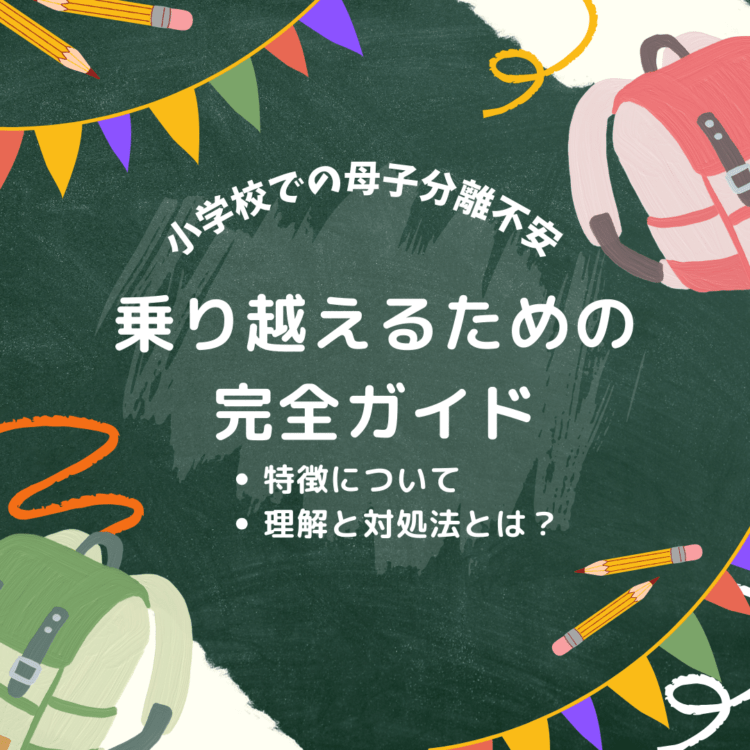子どもの医療においては、子ども自身の意見や意思決定権が尊重されるべきです。憲法や子どもの権利条約に基づき、医療関係者と保護者が子どもの最善の利益を考慮しながら話し合いを行うことが求められています。この記事では、子どもの自己決定権と意見表明権について解説し、重篤な疾患を持つ子どもの医療におけるガイドラインや話し合いの流れについて紹介します。
子どもの自己決定権と意見表明権の重要性

憲法では、個人の尊重と自己決定権の重要性が保障されています。この権利は、患者が医療に関する意思決定を行う際にも適用されます。特に子どもに対しては、子どもの権利条約に基づき、自己の意見を表明する権利が保障されています。
ただし、子どもの意見表明権は、年齢や成熟度に応じて考慮されます。医療行為は専門的な内容を含むため、子どもの理解力や判断能力によっては、意見表明が困難な場合もあります。そのため、保護者(親権者または未成年後見人)が子どもの代わりに意思決定をすることがあります。しかし、子どもの権利条約に従い、子どもに対しても適切な説明を行い、子の理解を得ることが必要です。
重篤な疾患を持つ子どもの医療におけるガイドライン
重篤な疾患を持つ子どもの医療においては、日本小児科学会がガイドラインを定めています。このガイドラインでは、子どもの気持ちや意見を最大限尊重し、治療方針を子どもの最善の利益に基づいて決定することが求められています。医療提供者は、子どもと保護者に対して正確な情報を提供し、子どもが自分の意見を自由に表明できる環境を作る必要があります。
日本小児科学会:重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン
医療の話し合いから意思決定までの流れ
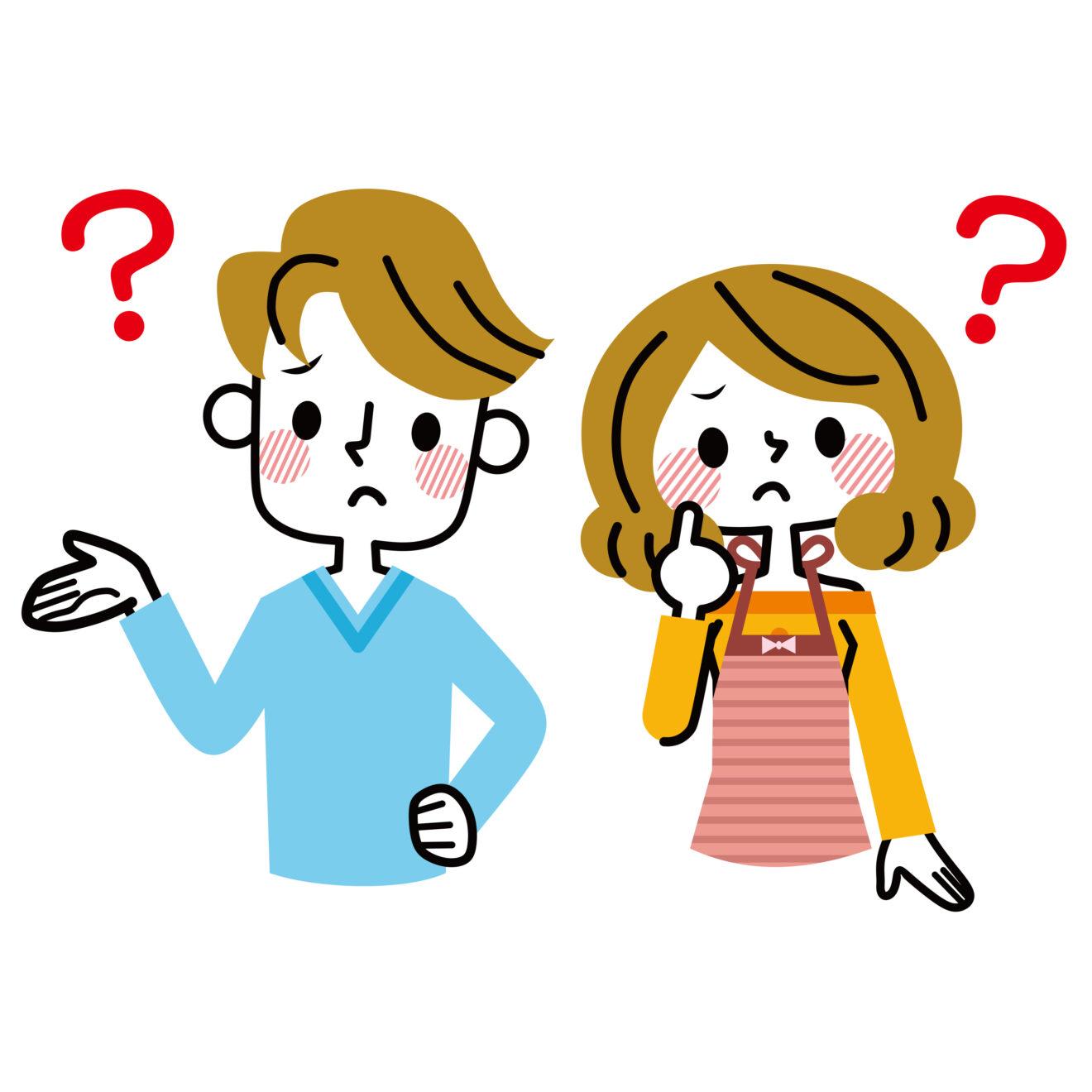
具体的な流れとしては、医療機関は子どもと保護者に対して適切な医療情報を提供し、子どもに分かりやすい説明を行います。子どもは自分の意見を表明し、保護者は子どもの意見を尊重しながら治療方針を決定します。この過程では、医療機関と子ども・保護者の間で対等な立場での話し合いが重要です。特に生命維持治療の差し控えや中止を検討する場合には、ガイドラインに従ったプロセスが遵守されます。
子どもの意見表明権と自己決定権を尊重しながら、医療提供者との話し合いを通じて最適な医療を受けることが重要です。医療機関は、子どもと保護者に対して情報を提供し、子どもの意見を十分に考慮した医療の提供に努めることが求められます。
| 提出先 | 医療機関 |
| 提出書類 | 医療機関による所定の同意書等 |
| 添付書類 | なし |
| 関連法令等 | 憲13、子どもの権利条約3・12、民820、重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン(平24・4・20公益社団法人日本小児科学会)、重篤な疾患を持つ新生児の家族と医療スタッフの話し合いのガイドライン(平成16年成育医療委託研究研究班) |
まとめ
子どもの医療においては、子ども自身の意見や意思決定権を尊重することが重要です。医療機関や医療提供者は、子どもと保護者との対話を通じて適切な医療情報を提供し、子どもの発達段階や理解能力に応じた意思表明を尊重しながら治療方針を決定することが求められます。子どもの最善の利益を考慮した医療の提供を通じて、子どもの健康と幸福な成長を支援しましょう。
こちらも参考にどうぞ
dekkun.に相談しよう