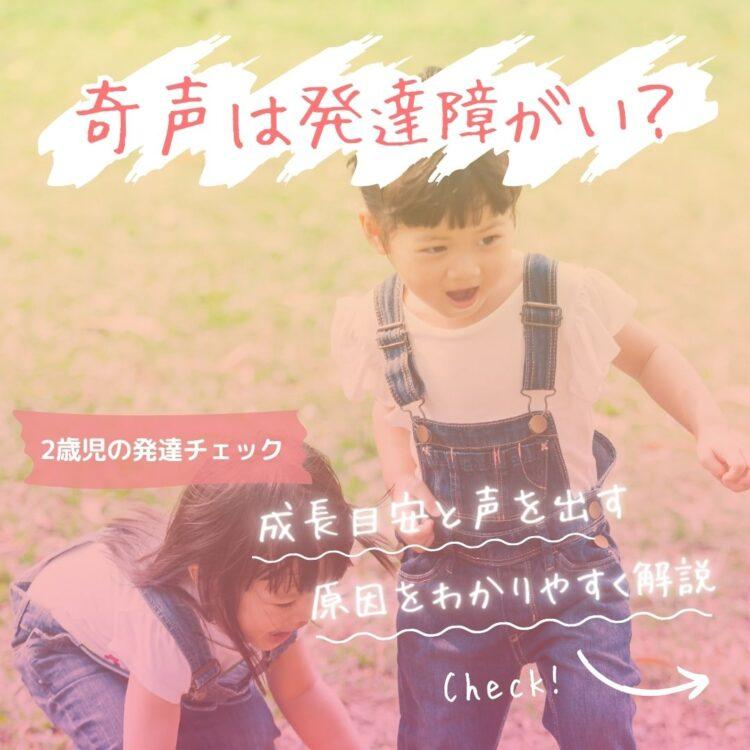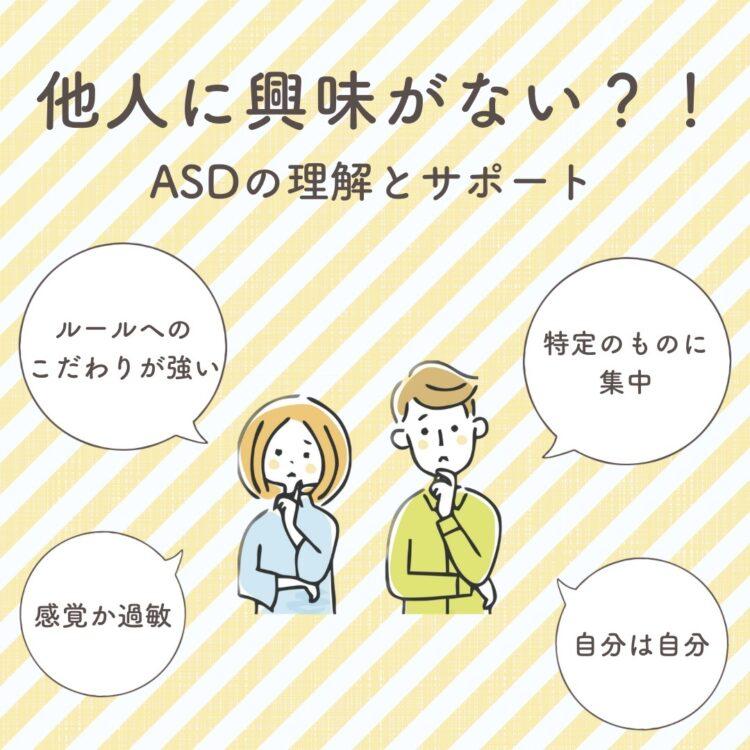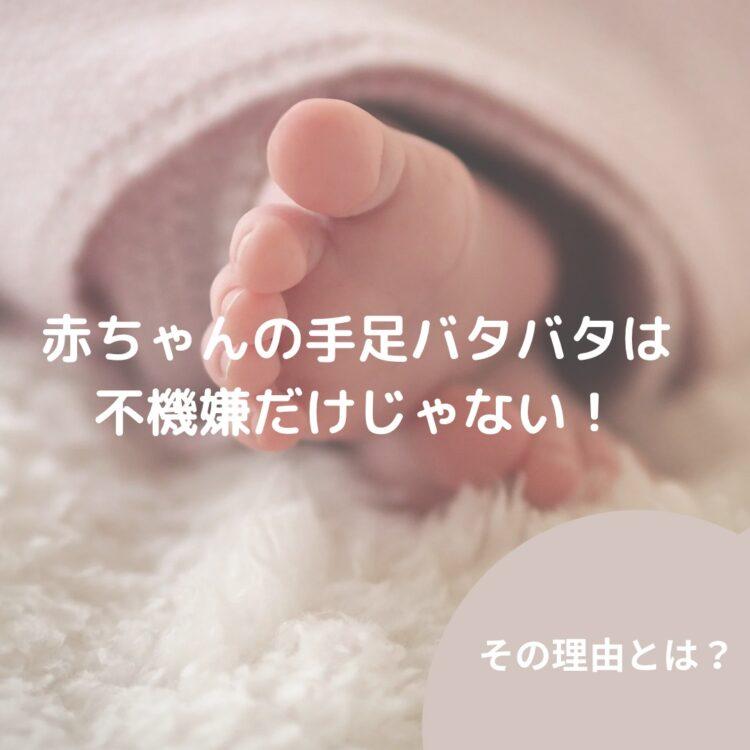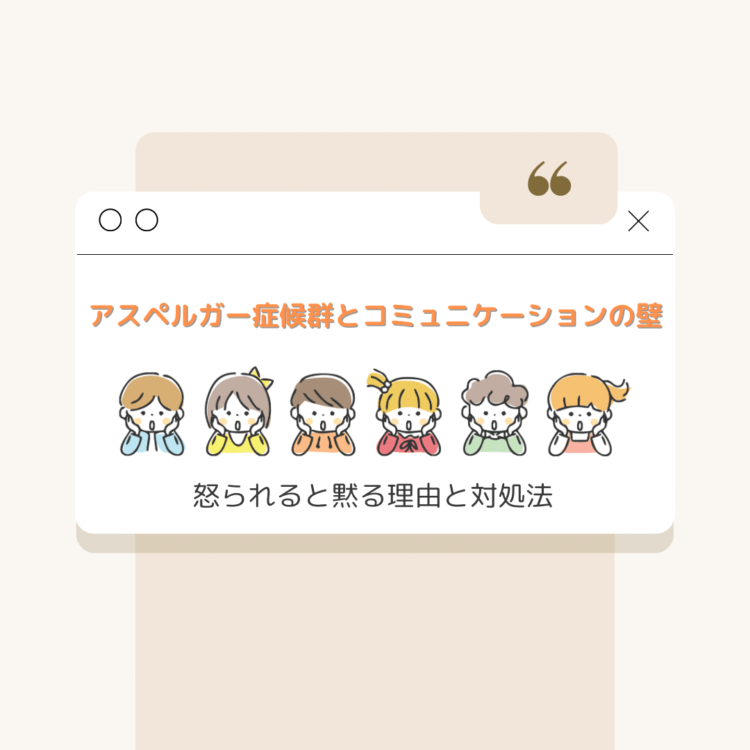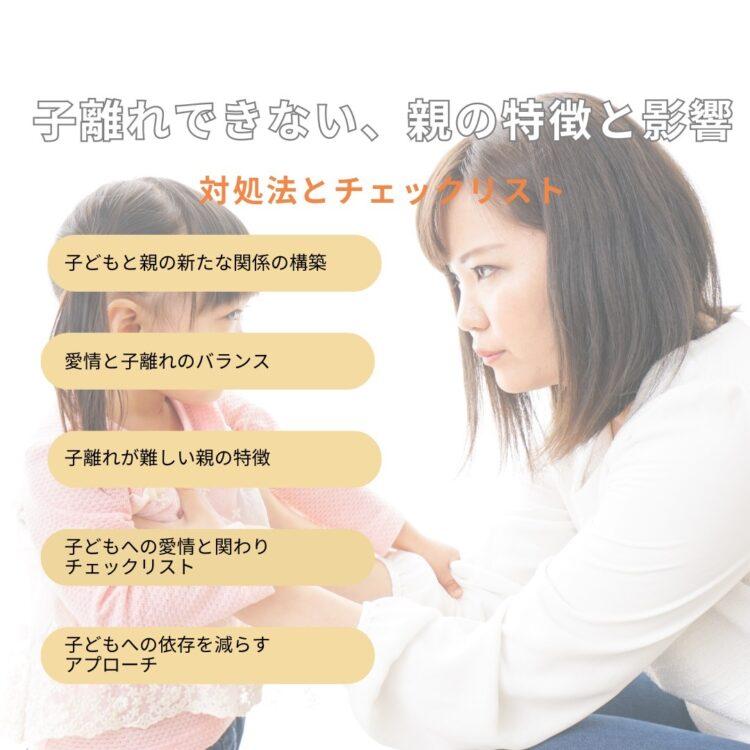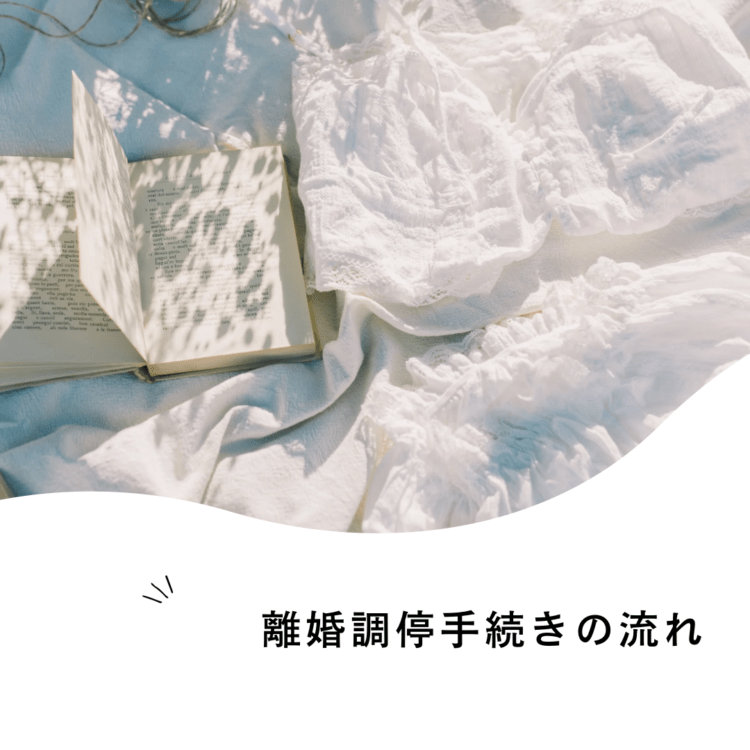家族は血のつながりだけでなく、愛と絆によって結ばれる特別な存在です。時には、血縁関係がない者と子供たちが心温まる絆を築くために、特別な養子縁組の道を選ぶことがあります。そんな特別な縁組の中でも、特別養子縁組は、養子となる者とその実親との親族関係が消滅し、新たな愛情とサポートが子供たちに注がれる素晴らしい制度です。本コラムでは、特別養子縁組の概要とその意義について探ってみましょう。
普通養子縁組制度の概要と申立権者

普通養子縁組は、実親との親子関係が終了しない形での養子縁組のことです。この制度は、養子が未成年の場合でも成人の場合でも利用することができます。ただし、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己または配偶者の直系の親族を養子にする場合は許可の必要はありません。また、配偶者がいる養親が未成年者を養子にする場合は、基本的に夫と妻の両方が養親として緑組をすることが必要です。
さらに、養子になる者が未成年であり、かつ、養親が後見人である場合、その点について家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所で普通養子縁組が許可された後、市区町村の戸籍課に養子縁組の届出を出すことで、養子縁組が正式に成立します。普通養子縁組の場合、届出の期間制限はありません。
申立権者
申立権者は養親となる者です。ただし、養子となる者が15歳未満の場合は、その法定代理人が未成年者に代わり縁組の承諾をすることが必要です。
特別養子縁組成立申立ての概要と申立権者

特別養子縁組とは、養子となる者とその実親との親族関係が消滅する養子縁組のことを指します。特別養子縁組を成立させるためには、次の2つの申立てが必要です。
| 特別養子適格の確認の申立て |
|---|
| 実親の同意や監護が相当でないことを審理する申立てです。 |
| 特別養子縁組の成立の申立て |
|---|
| 養親となる者が適当かどうかを審理する申立てです。 |
特別養子縁組の条件
特別養子縁組の条件として、実父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であり、その他特別の事情がある場合で、子供の利益のために特に必要があると認められる必要があります。例えば、実父母による虐待があった場合や代理母による出産の場合にも特別養子縁組が利用されます。
以前は特別養子縁組の申立ては養子が6歳未満でなければなりませんでしたが、現在は申立て時に15歳未満であればよく、15歳に達する前にやむを得ない理由で申立てできなかった場合は、18歳までに申立てが可能です。
実親の同意
特別養子縁組成立のためには、実親の同意が必要です。同意は出生後2か月経過後にされ、審問期日に同意されるか、または調査官の調査を経て裁判所に提出された場合、同意がなされた時点から2週間を経過すると撤回できなくなります。同意の撤回が制限されています。
養親について
養親となる者は配偶者がいる場合は夫と共に、養親は25歳以上でなければなりません(一方が25歳に達していれば、もう一方は20歳に達していれば養子縁組できます)。
養親候補者が養子となる未成年者を6か月以上監護した状況が考慮されます。そのため、養子縁組前に養親候補者と養子候補者が一緒に暮らす試験養育期間が必要となります。また、養子候補者が15歳以上の場合には、養子候補者の同意も必要です。
特別養子縁組成立の判が確定した日から10日以内に市区町村の戸籍課に特別養子縁組の届出を行う必要があります。
特別養子縁組においては、実父母に関する情報を十分に持っていないことや、実父母と対立する可能性があるため、特別養子適格の確認の申立てには児童相談所長が利害関係人として参加し、特別養子縁組成立の申立てには養親候補者が申立人となる場合には児童相談所長が中立人となることがあります。里親候補者が特別養子適格の確認の申立てと特別養子縁組成立の申立てを行う場合は、同時に行わなければなりません。また、特別養子適格の確認の審判が児童相談所長により申し立てられた場合、特別養子縁組成立の申立ては特別養子適格の確認の審判が確定してから6か月以内に行わなければなりません。
申立て対応までの流れ
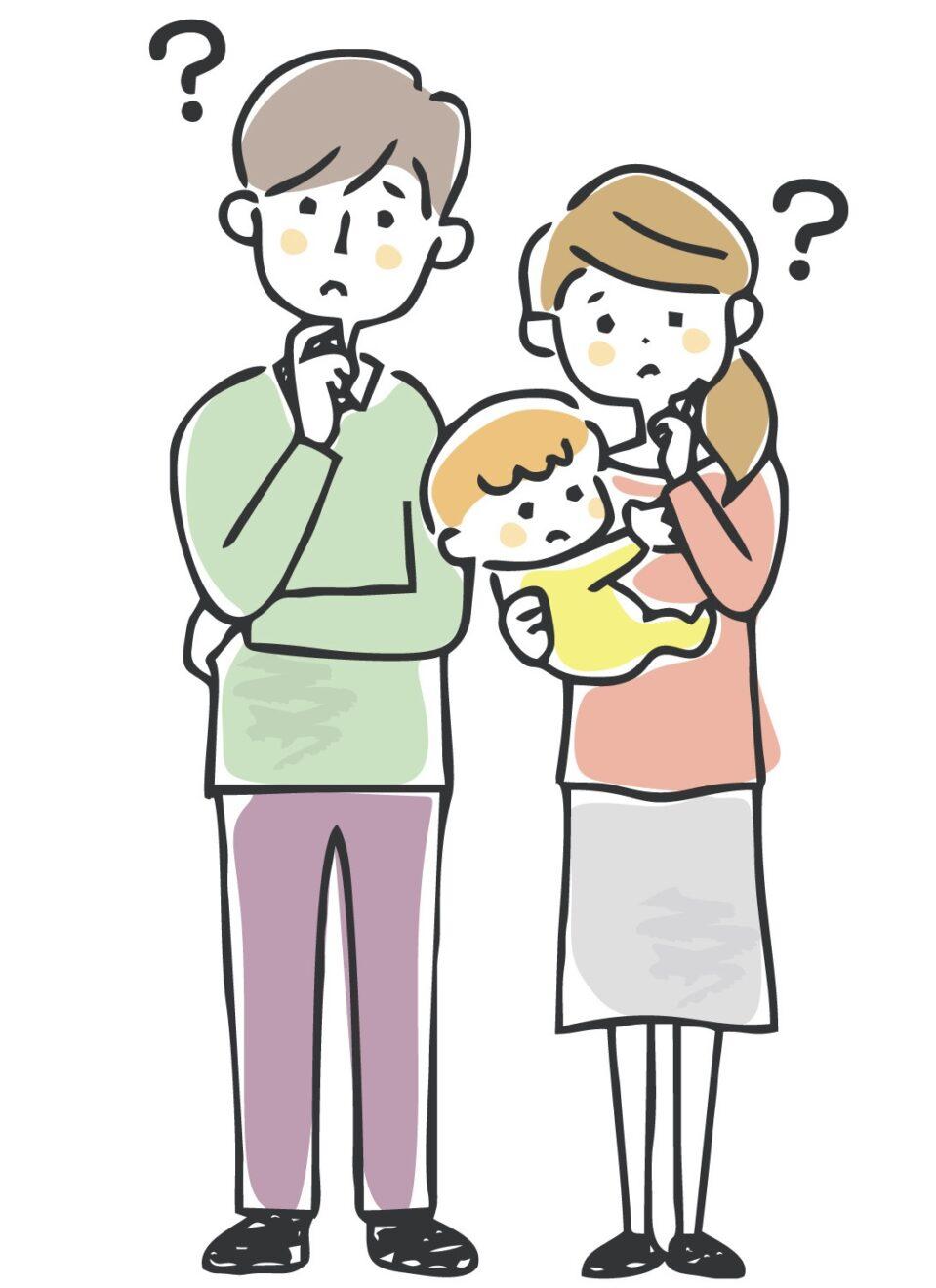
申立先
普通養子縁組の場合
養子となる者の住所地を管轄する家庭
特別養子縁組の場合
- 養親候補者が申し立てる場合には養親となる者の住所地を管縮する家庭裁判所
- 児童相談所長が申し立てる場合には養子となる者の住所地を管轄する
提出書類
普通養子縁組の場合
養子縁組許可申立書
特別養子縁組の場合
特別養子適格確認申立書、特別養子縁組申立書
添付書類
普通養子縁組の場合
- 申立人(養親となる者)の戸籍謄本、未成年者の戸籍謄本
- 未成年者が15歳未満の場合、代諾者(法定代理人)の戸籍謄本
- 養子となる者1人につき収入印紙800円分、郵便切手
特別養子縁組の場合
特別養子適格確認の申立て
- 養子となる者の戸籍謄本
- 養子となる者の実父母の戸籍謄本
- 郵便切手
※なお、特別養子適格確認の申立ての場合には印紙は不要
特別養子縁組成立の申立て
- 養親となる者の戸籍謄本
- 養子となる者1人につき収入印紙800円分、郵便切手
関連法令等
普通養子縁組の場合
民794・795・797①・798
特別養子縁組の場合
民817の2~817の11、戸籍63・68の2、家164②
| 普通養子縁組の場合 | 特別養子縁組の場合 | |
|---|---|---|
| 申立先 | 養子となる者の住所地を管轄する家庭 | ・養親候補者が申し立てる場合には養親となる者の住所地を管縮する家庭裁判所 ・児童相談所長が申し立てる場合には養子となる者の住所地を管轄する |
| 提出書類 | 養子縁組許可申立書 | 特別養子適格確認申立書、特別養子縁組申立書 |
| 添付書類 | ・申立人(養親となる者)の戸籍謄本、未成年者の戸籍謄本 ・未成年者が15歳未満の場合、代諾者(法定代理人)の戸籍謄本 ・養子となる者1人につき収入印紙800円分、郵便切手 | 特別養子適格確認の申立て ・養子となる者の戸籍謄本 ・養子となる者の実父母の戸籍謄本 ・郵便切手 ※なお、特別養子適格確認の申立ての場合には印紙は不要 特別養子縁組成立の申立て ・養親となる者の戸籍謄本 ・養子となる者1人につき収入印紙800円分、郵便切手 |
| 関連法令等 | 民794・795・797①・798 | 民817の2~817の11、戸籍63・68の2、家164② |
まとめ
特別養子縁組は、愛と絆をつなぐ特別な道として、多くの子供たちに新たな家族の輪を広げています。実父母との関係が困難な場合や特別な事情がある場合でも、子供たちに幸せな未来を提供するために選択される特別養子縁組の素晴らしさには目を見張るものがあります。特別養子縁組においては、子供たちの利益と幸福が最優先とされることを忘れずに、丁寧な申立てと試験養育期間を経て、新たな家族の絆を築いていくことを願っています。特別養子縁組がもたらす愛情と支えが、子供たちの未来に輝きをもたらすことを信じています。
dekkun.に相談しよう