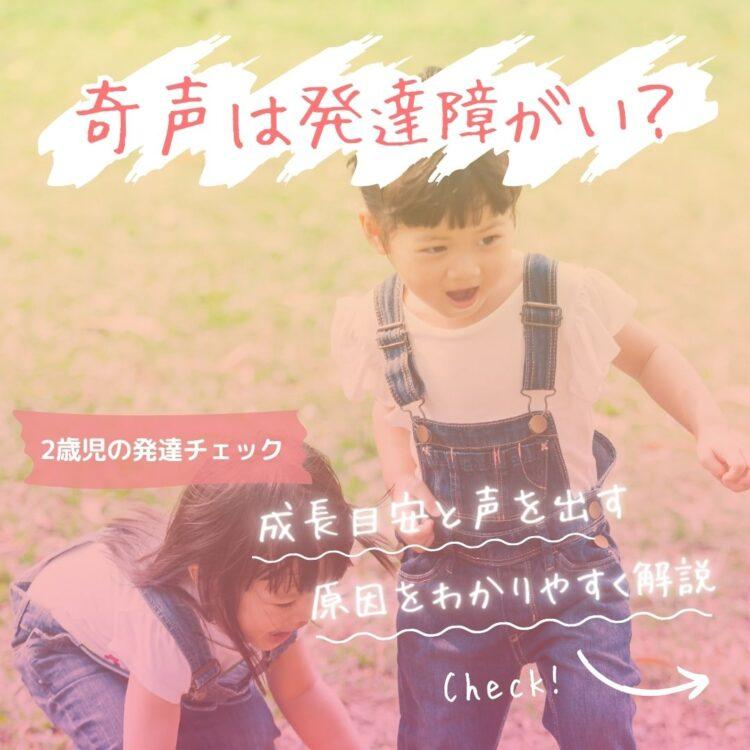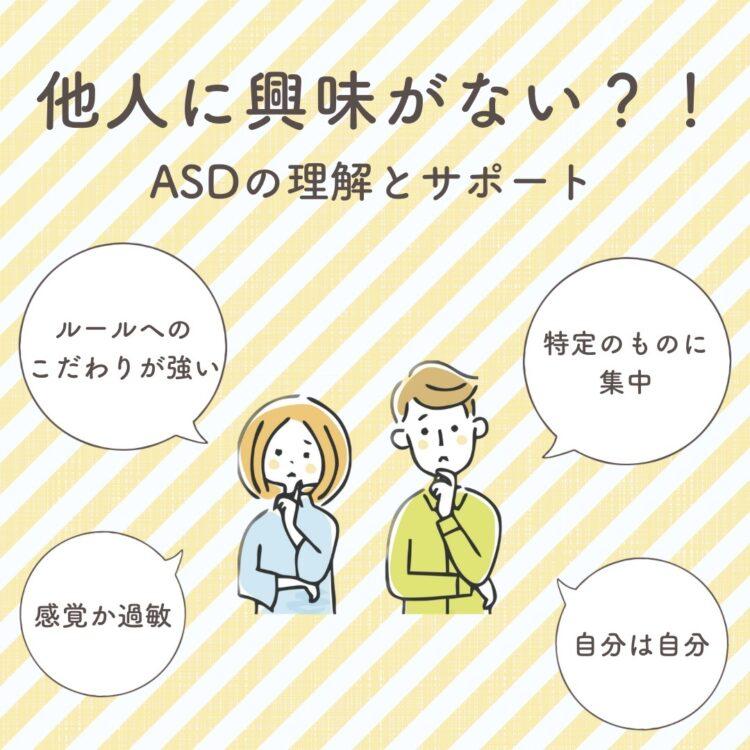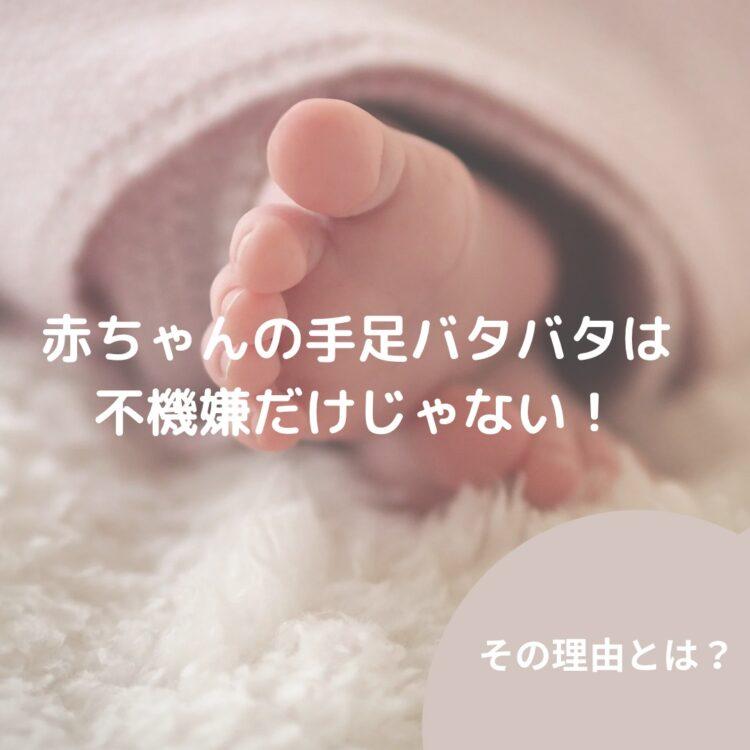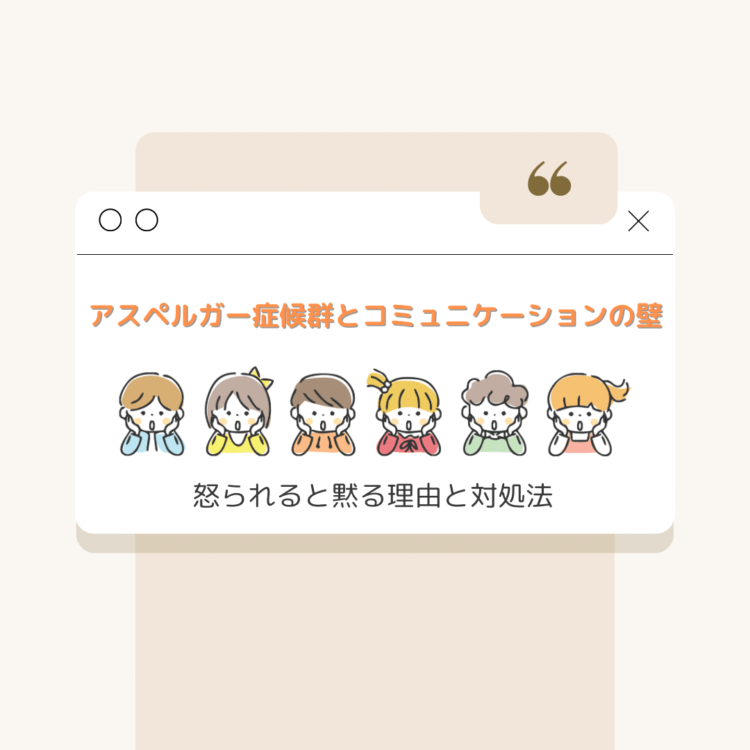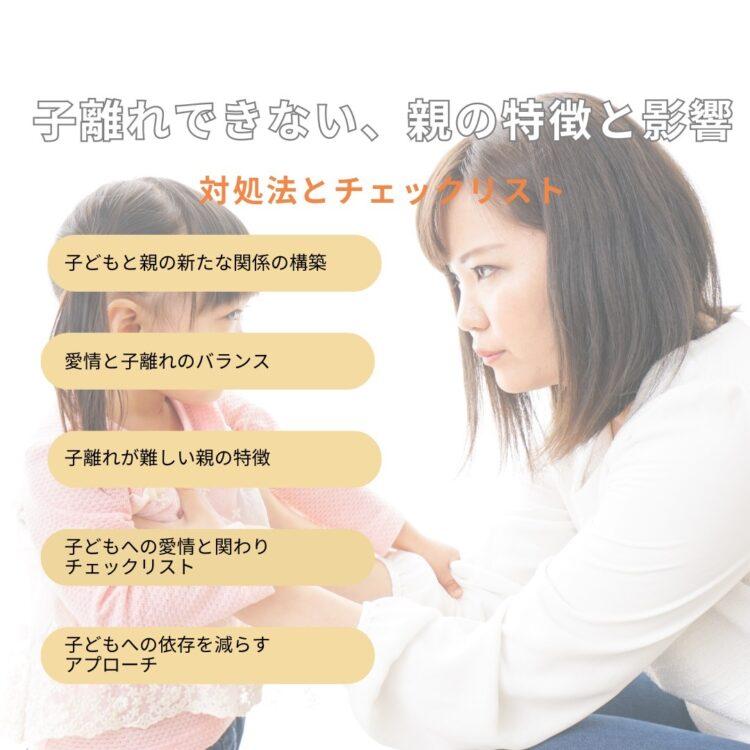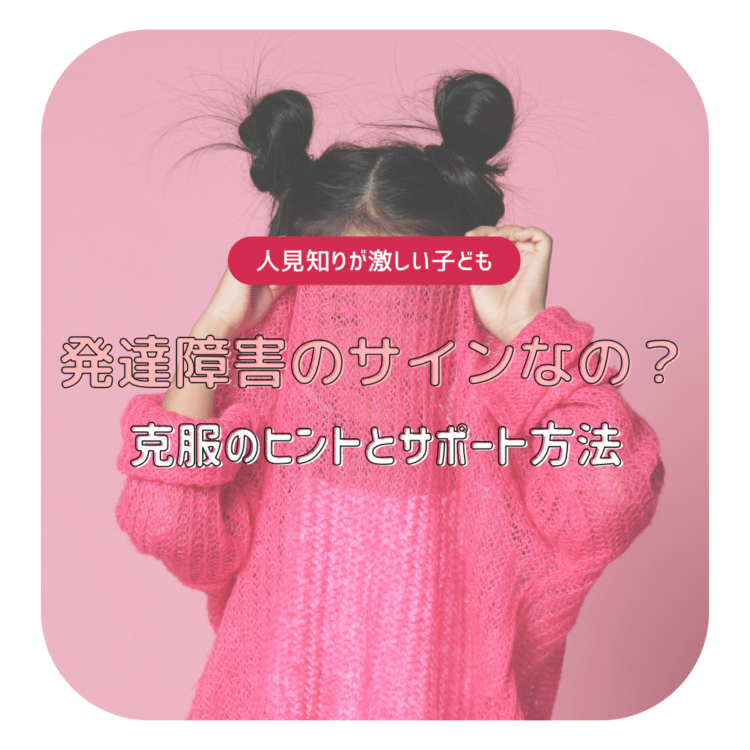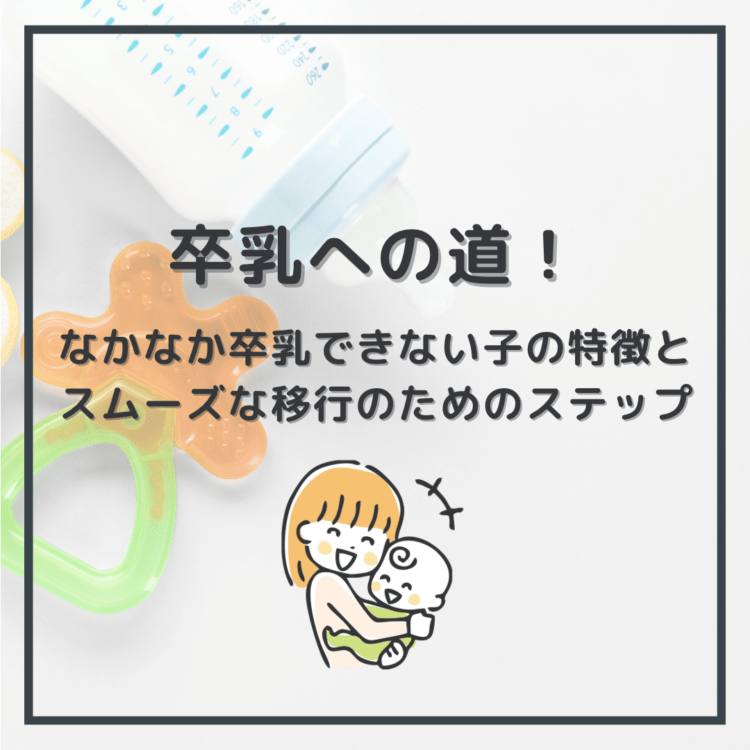子どもの成長には個人差があり、発達が気になる親御さんにとっては忘れ物の悩みが増えることもあります。子どもが忘れ物をするのは成長の一環であり、親御さんの優しいアシストが必要です。このコラムでは、子どもの発達に気を配る親御さんに向けて、忘れ物を防ぐためのアシスト術をご紹介します。
子どもの発達に気にかける親御さんへ

子どもの発達には個人差があり、成長過程での忘れ物はよくあることです。しかし、発達が気になる親御さんにとっては、その悩みが増大することもあります。安心してください。今回は忘れ物を防ぐための優しいアシスト術をお伝えします。
発達グレーゾーンの子どもにも、忘れ物対策は効果的

発達グレーゾーンの子どもにとって、忘れ物はさらなる悩みの種となることがあります。しかし、親御さんのサポートがあれば、その悩みを軽減することができます。一緒に取り組んでみましょう。子どもの発達を気にかける親御さんへ、以下に忘れ物を防ぐためのアシスト術をご紹介します。
家族の声かけが重要
毎朝、家族全員で持ち物の確認をする習慣を作りましょう。子どもの発達に合わせて、優しく声をかけてリマインドしましょう。
学校との連携を大切に
学校の先生に忘れ物対策のお願いをしてみましょう。学校からの持ち帰り物も忘れてしまうことがあるかもしれませんので、先生にお願いして家に帰る直前に一声かけてもらうと良いですね。
忘れ物を防ぐための優しいアシスト術
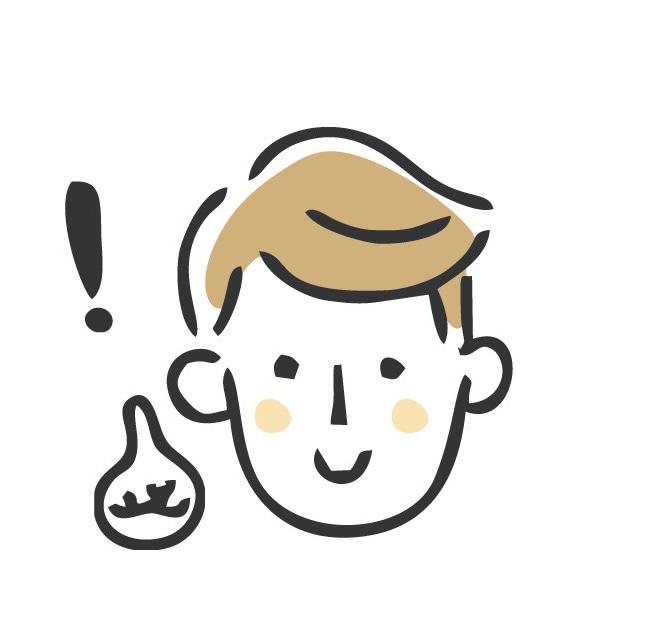
続いて、忘れ物を防ぐためのアシスト術をご紹介します。
親子の協力で成長を促す
子どもが忘れ物をしないようにするためには、親御さんのサポートが不可欠です。積極的に子どもをアシストし、持ち物のチェックや準備を手伝いましょう。子どもの成長を共に喜びながら、忘れ物のストッパーとなりましょう。
可視化と整理
リストやカレンダーなどの可視化ツールを活用し、持ち物のチェックリストやスケジュールを作成しましょう。また、整理整頓の習慣を身につけるために、専用の収納場所やラベルを活用すると効果的です。
発達障害と忘れ物の関係
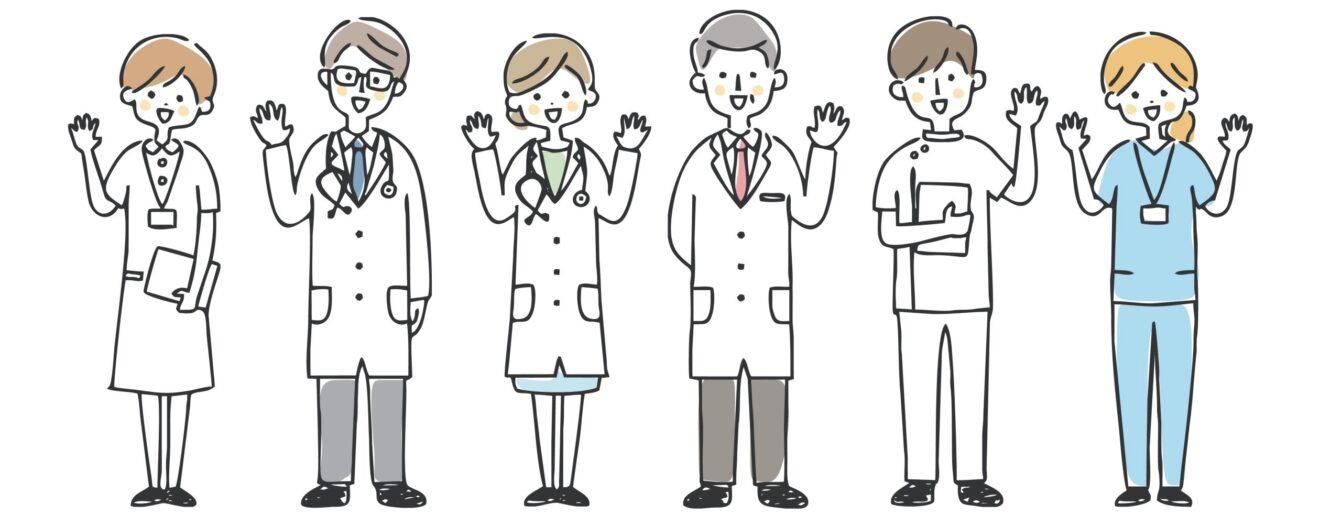
発達障害を抱える子どもたちは、注意力や集中力の課題があるため、忘れ物をするリスクが高くなります。例えば、注意欠陥・多動性障害(ADHD)を持つ子どもは、思いつきが多く忘れ物が増える傾向があります。また、自閉スペクトラム障害(ASD)を抱える子どもたちは、持ち物の整理やルーティンの変更に苦労しやすいため、忘れ物が発生しやすいです。発達障害の種類によって異なる特性がありますが、親御さんのサポートが重要となります。
まとめ
発達に関するグレーゾーンを抱える子どもたちの忘れ物のリスクは高いですが、親御さんの優しいアシストと適切な対策によって、その悩みを軽減することができます。発達に関するグレーゾーンの特性を理解し、声かけや整理整頓の手法を活用することで、子どもたちの忘れ物を防ぐ力を育んでいきましょう。親子の絆とサポートの連携によって、子どもたちは忘れ物の悩みから解放され、充実した学校生活を送ることができるでしょう。
dekkun.に相談しよう