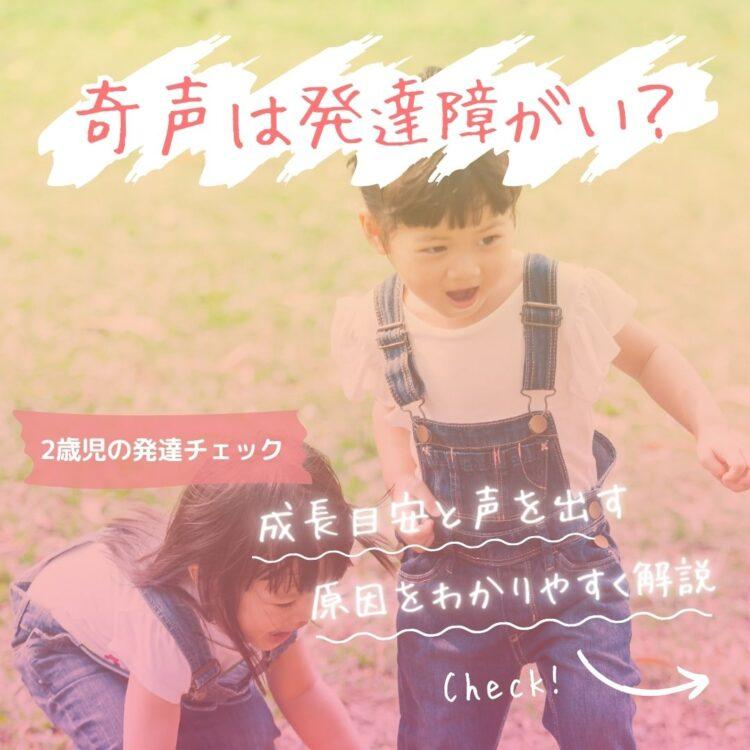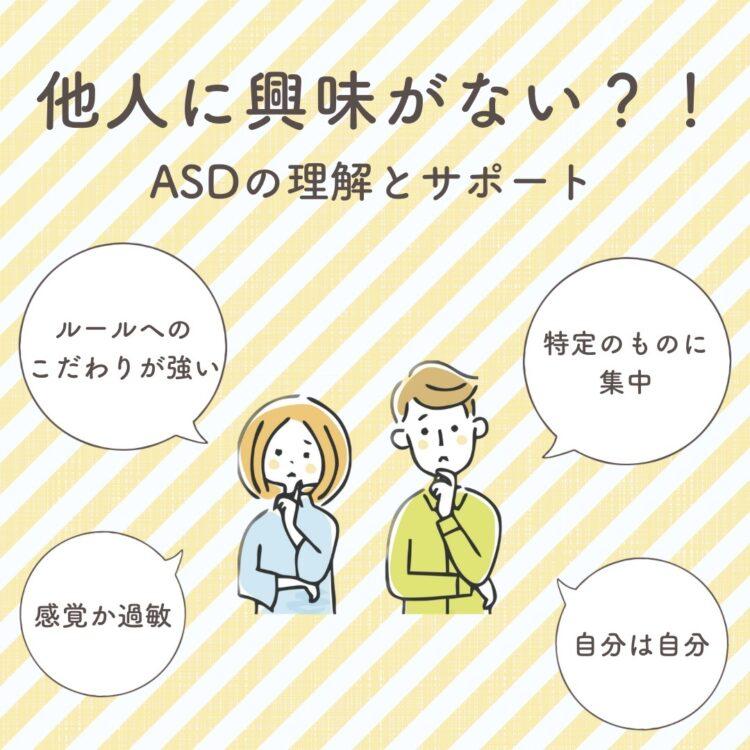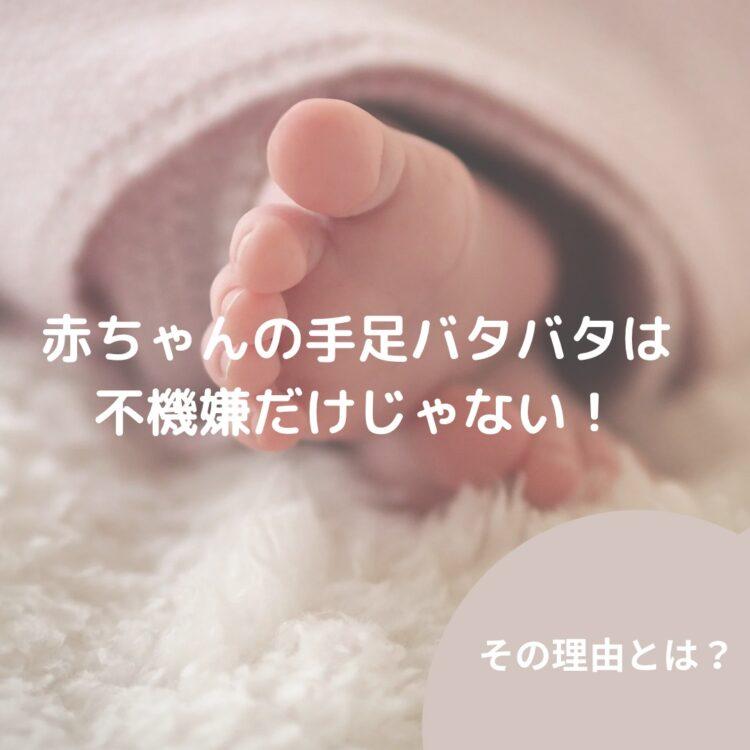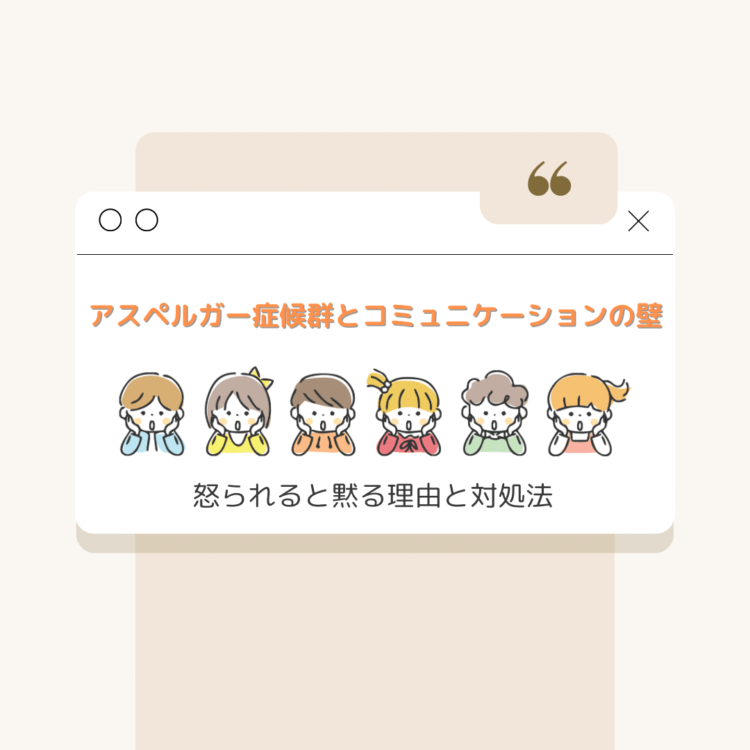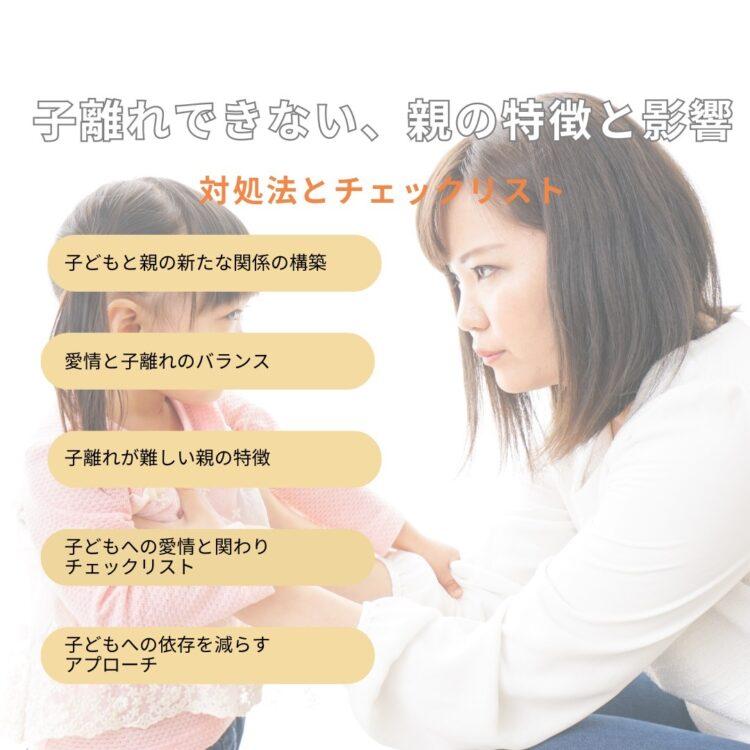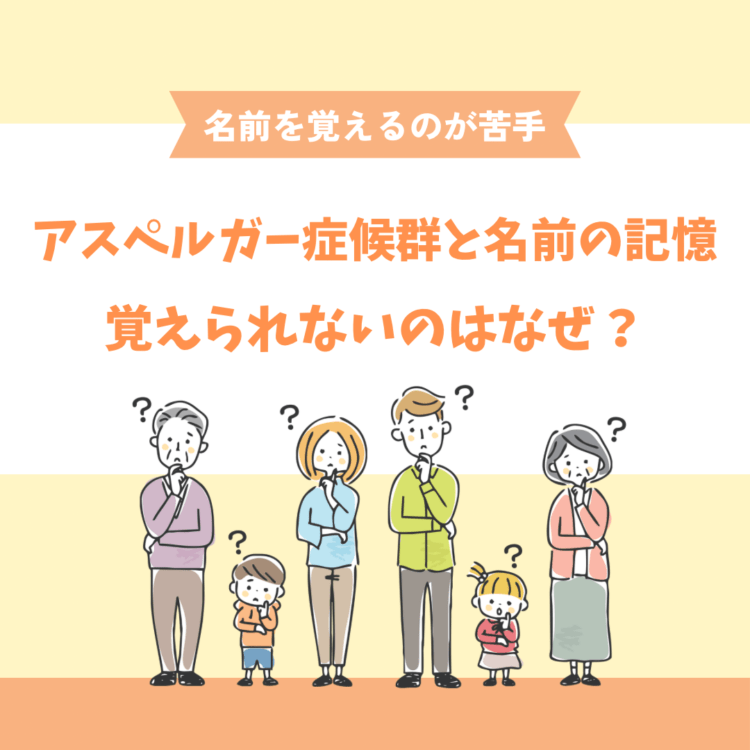ワーキングメモリの向上が子どもの学習や社会的な側面に与える重要性と、個人差があることを理解することが大切です。ワーキングメモリが低い子を持つ親御さまへ、改善方法と注意点をご紹介します。子どもの脳を鍛えたいと考える皆さん、ぜひお読みください。
ワーキングメモリの向上は可能
ワーキングメモリ(動作記憶)とは、情報を一時的に記憶し、選別・処理する脳の重要な能力です。例えば、会話では話の内容を一時的に記憶し、必要な情報を抽出して返答を考えるといった働きを担っています。
人々のメモリの大きさには個人差があり、「机の大きさ」に喩えられます。メモリが大きい子供は広い机のように多くの情報を同時に処理できますが、メモリが小さい子供は限られた情報しか保持できません。
しかし、初めはメモリが低い子供でも改善の余地はあります。トレーニングを通じて少しずつ脳の働きが向上し、ワーキングメモリが強化されると考えられています。ここでは、ワーキングメモリを向上させるための方法とその重要性についてご紹介します。親御さま方はぜひ参考にしてください。
子どものワーキングメモリが低いと起こる困りごと
個人差があるワーキングメモリですが、機能が低下していると、日常生活において困難が生じます。会話や学習などに「短期記憶」や「判断力」は欠かせませんが、動作記憶の能力が低い子どもは情報を覚えたり処理したりするのが苦手で、問題が生じるようです。
| ワーキングメモリが低いと起こる困りごと |
|---|
| 日常生活で物事を忘れることが増える。 |
| 複雑な指示やタスクを同時に覚えられない。 |
| 異なる作業や状況に適応する際に困難を抱える。 |
| 学習やアカデミックなタスクにおいて挑戦を経験する。 |
| 情報を整理し、整然と処理するのが難しい。 |
| 口頭で伝えられる情報を正確に記憶することが難しい。 |
これらの困りごとは、ワーキングメモリが低いことに起因します。例えば、「忘れ物が多い」「勉強が覚えられない」といった記憶面のトラブルや、「頭の切り替えが苦手」「色々なことを言われると、頭の中が混乱する」ような情報処理の力の不足によるトラブルが代表的です。親御さまは子供の困りごとを理解し、ワーキングメモリの向上に向けて適切なサポートを提供することが重要です。
子どものワーキングメモリが低くなる要因とは
ワーキングメモリには個人差があり、その差が生じる原因は様々です。子供のワーキングメモリが低くなる要因として、以下のような要素が考えられます。これらの要因を理解することで、改善方法を考える際に役立つでしょう。
発達障がいがある
発達障がいを持つ子供は、ワーキングメモリが低い傾向があるとされています。発達障がいの原因はさまざまですが、基本的には脳の働きに問題があるとされ、それが記憶や情報処理にも影響を与えると言われています。
特に、ADHDを持つ子供はワーキングメモリが低い傾向があります。ADHDは「集中力が続かない」「忘れものが多い」といった特性があり、脳機能の低下している人の特徴にも似ています。
また、ADHDは前頭前野の働きが原因とされ、この点からも関係性が指摘されています。動作記憶は海馬や前頭前野の働きが関わっているため、前頭前野の働きに問題があると、ADHDやメモリの低下が現れると考えられます。
神経疾患の影響
神経疾患がある場合も、ワーキングメモリが低くなる可能性が高いとされています。神経疾患とは、脳や脊髄、神経などが正常に機能しなくなる病気の総称です。運動や滑舌の問題が主な症状として現れることもありますが、もの忘れを伴う場合もあります。
特に、アルツハイマー病を患っている場合はメモリが低くなりやすいと考えられます。アルツハイマー病は、前頭葉の働きに問題が生じる認知症の一種です。動作記憶は前頭葉の働きにも関わっているため、アルツハイマー病によって前頭葉に問題が生じると動作記憶の力も低下します。
不十分な睡眠・睡眠障がい
睡眠に問題がある場合も、ワーキングメモリが低くなる可能性があります。睡眠不足になると、前頭葉や頭頂葉の活動量が減少し、正常に機能しなくなることがあります。前頭葉や頭頂葉の活動は、記憶・判断・情報処理に大きく影響するため、動作記憶の力も低下するのです。
睡眠障がいで眠れない日が続いた場合も、同様の状態になります。睡眠障がいの原因には、精神的なストレスや寝具の相性、糖尿病やアレルギー疾患などが含まれますが、睡眠不足の状態に陥ることが共通しています。睡眠不足になると脳がうまく機能せず、動作記憶の力も低下してしまうのです。
ストレスの影響
ストレスのある環境での生活も、ワーキングメモリが低くなる原因となることがあります。ストレスは脳の萎縮や過活動などを引き起こし、前頭前野などの脳の機能を損傷させてしまうことが原因です。
子どもの場合、学習や学校生活が主なストレスの原因となります。成績が思うように上がらなかったり、人間関係が上手くいかなかったりと、学校で受けるストレスはさまざまです。学校生活におけるストレスは長期間続くことがあり、脳にも大きな影響を及ぼす可能性があるのです。子供たちのストレスを理解し、適切にサポートすることが重要です。
子どものワーキングメモリを改善する5つのアプローチ
子どものワーキングメモリを改善するために、以下の5つのアプローチがあります。それぞれのアプローチを工夫して取り組むことで、メモリの向上を促進できるかもしれません。
必要な睡眠を確保する
十分な質と量の睡眠をとることは、ワーキングメモリの向上に不可欠です。
記憶力を刺激する
記憶に関連するゲームや活動を取り入れることで、ワーキングメモリを鍛えることができます。
身体を活動させる
適度な運動を取り入れることで、脳の血流が改善され、ワーキングメモリも向上します。
複数のタスクをこなす
複数のタスクを同時に行うことで、ワーキングメモリに負荷をかけることができます。例えば、同時に二つのことをする「デュアルタスク」のような形で行うと理解しやすいかもしれません。
ストレスを軽減する
ストレスのある環境を改善し、リラックスした状態を保つことで、ワーキングメモリの機能向上に寄与します。
子どものワーキングメモリを改善する際の3つのポイント
子どものワーキングメモリを改善する際には、以下の3つのポイントに留意することが大切です。メモリが低い子どもが改善トレーニングを行う際に、気をつけるべき注意点を解説します。
楽しみながらストレスを感じさせない
子どものワーキングメモリを改善する際は、トレーニングを楽しく、ストレスを感じさせないようにしましょう。無理な負荷やプレッシャーは避けて、子どもが取り組むのを楽しんで行えるように心掛けましょう。楽しさがモチベーションを高め、ワーキングメモリの向上をスムーズに促進します。
ゆっくり進めて成果を待つ
ワーキングメモリの改善は時間がかかることがあります。子どもの脳は成長段階にあるため、変化には個人差があります。焦らずゆっくりとトレーニングを進め、成果をじっくりと待ちましょう。少しずつ変化が見られることもありますので、辛抱強く取り組むことが大切です。
少ない指示で負担を軽くする
ワーキングメモリが低い子どもは、多くの情報を一度に処理するのが難しい場合があります。トレーニングは少ない指示や簡単なタスクから始め、子どもの負担を減らすことが重要です。徐々に難易度を上げながら進めることで、子どもが無理なく楽しく取り組めるようにしましょう。
まとめ
ワーキングメモリは、日常生活において重要な「思考力」「判断力」「記憶力」に関わる脳の働きです。個人差があるものの、メモリが低い場合でも適切なトレーニングで改善できます。
しかし、改善トレーニングを行う際には過度な負担をかけないように注意が必要です。脳に負荷をかけたりストレスを感じさせると状況が悪化する可能性があります。子どもの特性に合わせて長期的に続けやすい形でトレーニングを行いましょう。
dekkun.に相談しよう